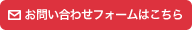風邪を引きやすかったり、体調を崩しがちだったりと、近年では健康に自信のない方が増えているようです。その背景には「低体温」という共通点があります。体温と免疫力の関係を見ていきましょう。
体温が下がると免疫力が低下するのはなぜ?
その理由は、体内に侵入したウイルスや細菌を攻撃する白血球の活動が抑えられるため。白血球は血液にのって体内をパトロールし、病原菌や異物、がん細胞までも攻撃してくれる健康維持に欠かせない存在です。しかし、カラダが冷えて体温が下がると、血管が収縮して血行不良になり、白血球の活動も低下してしまうことに。すると、病原菌をはじめとした敵からカラダを守ることができず、病気を発症しやすくなるのです。反対に、体温が上がって血液の流れが良くなると、白血球が動きやすくなって敵と戦う力が強くなり、病気にかかりにくくなるとされています。体温が免疫力に与える影響はとても大きく、体温が1度下がると免疫力は30%低下し、反対に1度上がると一時的ではありますが、免疫力は5~6倍にもなると言われています。このように、体温が下がると単に風邪をひきやすくなるということだけではなく、がんになる確率も上がるとまでいわれています。
現代人は低体温になりがち、その原因は「筋力不足」と「食生活」
現代人は低体温に陥りがちです。食事やストレスなどさまざまな原因が考えられますが、その最たるものが、筋力不足と食生活です。低体温によって免疫力が低下すると、疲れやすくなったり、風邪を引きやすくなったりして、慢性的に不調が続くケースも少なくありません。
現代の便利な生活がもたらす筋力低下
カラダの熱を生産する筋肉は、体温の維持に欠かせないもの。筋肉量が減少すると、体温の低下にもつながります。現代人は昔と比べて慢性的な運動不足に陥りがち。家電製品や乗り物の登場によって暮らしはずいぶん便利になりましたが、その代償として運動量は減少する一方です。便利な生活と引き換えに筋力の低下を招き、昔よりも低体温な人が増えるようになったと考えられます。
身のまわりにあふれるカラダを冷やす食材
私たちの身のまわりには、カラダを冷やす食材がたくさんあります。知らずに食べていると、冷えやすい体質になっていることも。特に注意したいのが、白砂糖や小麦を含む食品です。お菓子やパンなど口にしやすいものが多く、嗜好性が強いため、食べすぎてしまう傾向があります。また、トマトやレタスなどカラダに良さそうな食材も、カラダを冷やす効果があるので摂取量には気をつけましょう。
筋力をつけて体温維持ができるカラダづくりを
体温を上げるためには、筋肉量を増やしたいところ。生活のなかで運動習慣をつけて、筋力アップを目指しましょう。おすすめは、30分程度のウォーキングやサイクリングなどの有酸素運動と、スクワットを中心とした軽い筋トレ。血流を良くする有酸素運動に加えて、筋肉を鍛える筋トレを並行することで、体温維持がしやすいカラダに近づきます。下半身は全身のなかでも大きな筋肉が集まっている場所なので、筋肉量を増やすのに効果的な部位。腹筋や体幹の筋トレに偏りがちな人は、1日10回程度でOKなので、下半身の筋トレもぜひ取り入れてみてください。
温まる食品で内側からカラダを温める
カラダを冷やす食品を避けるだけでなく、温める食品を取り入れることも重要です。
金時生姜
カラダを温める食品の代表格といえるのが生姜です。生姜の辛味成分「ジンゲロール」には、血行を良くする働きがあり、カラダを温めるよう働きかけます。なかでも、金時生姜には多くの「ガラノラクトン」が含まれており、血管拡張作用が期待できます。
高麗人参
血圧の調整に働きかけるサポニンを豊富に含む高麗人参は、冷えの予防に効果的とされています。また、免疫力を高めることでも知られており、滋養強壮のために摂取する人が多い食品です。
ヒハツ
血流を上げて手足の部分冷えに働きかける、冷え対策で注目の食品。コショウの一種で、沖縄そばに使われることでも知られています。豚肉料理とも相性が良く、日ごろの食事にも取り入れやすいでしょう。
牛肉の赤身・ラム肉
肉類を食べるときは、牛肉の赤身やラム肉がおすすめ。これらの肉には、L−カルニチンと呼ばれる成分が含まれており、細胞の熱産生を促し、カラダを温める作用が期待できます。
運動と食事で冷えないカラダへ
何かと冷えやすい現代人は、運動や入浴、食事で体温を高めるカラダづくりを意識したいもの。体温を上げて免疫力を高めることで、病気にかかりにくくなるだけでなく、毎日をいきいきと過ごせるようになるでしょう。生活習慣や食事を見直しつつ、生姜をはじめとしたカラダを温める食品を積極的に取り入れて、健やかなカラダを目指しましょう!
ポイント
体温は免疫力に重要な影響を及ぼします。体温が低い方は、適切な運動とカラダを温める食品の摂取を心がけましょう。